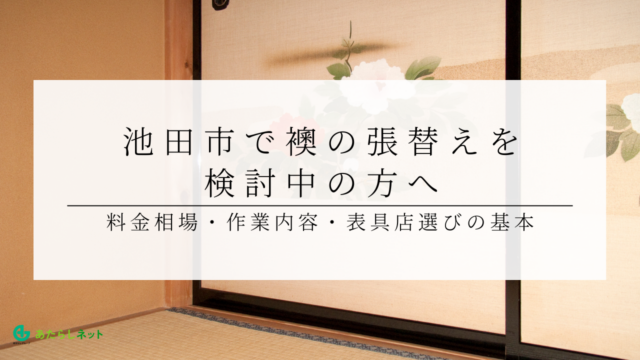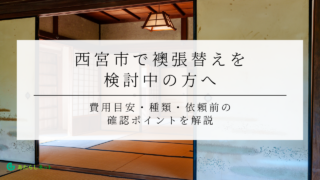襖に黒ずみやシミのような汚れが出て、「これってカビ?」と不安になったことはありませんか?
でも実際には、こんな悩みを抱えている方が多いはずです。
- 襖にカビが生えてしまったけど、どう掃除すればいいか分からない
- 拭き取ってもまたカビが出てくる…再発を防ぐ方法を知りたい
- そろそろ張り替えた方がいいのか、判断に迷っている
実は、襖に発生するカビは湿気や生活習慣の積み重ねによって発生しやすく、正しい除去方法と予防策をとることで再発を防ぐことができます。
この記事では、原因・除去・予防・張替えの判断ポイントまでをわかりやすく解説。
和室を清潔に保ちたい方に役立つ実践的な知識が得られます。

襖の張替えは、信頼できる専門業者に相談するのが安心です。「あたらし(国家資格職人が丁寧施工)」なら、再発を防ぐ防カビ対応の張り替えをご提案いたします!見積無料!スピード対応!
電話番号:0120-6767-23
(※営業時間外は留守番電話で受付)
\受付時間/午前7:00〜(土日祝日も対応)!/
放置NG!襖にカビが発生する主な原因とは
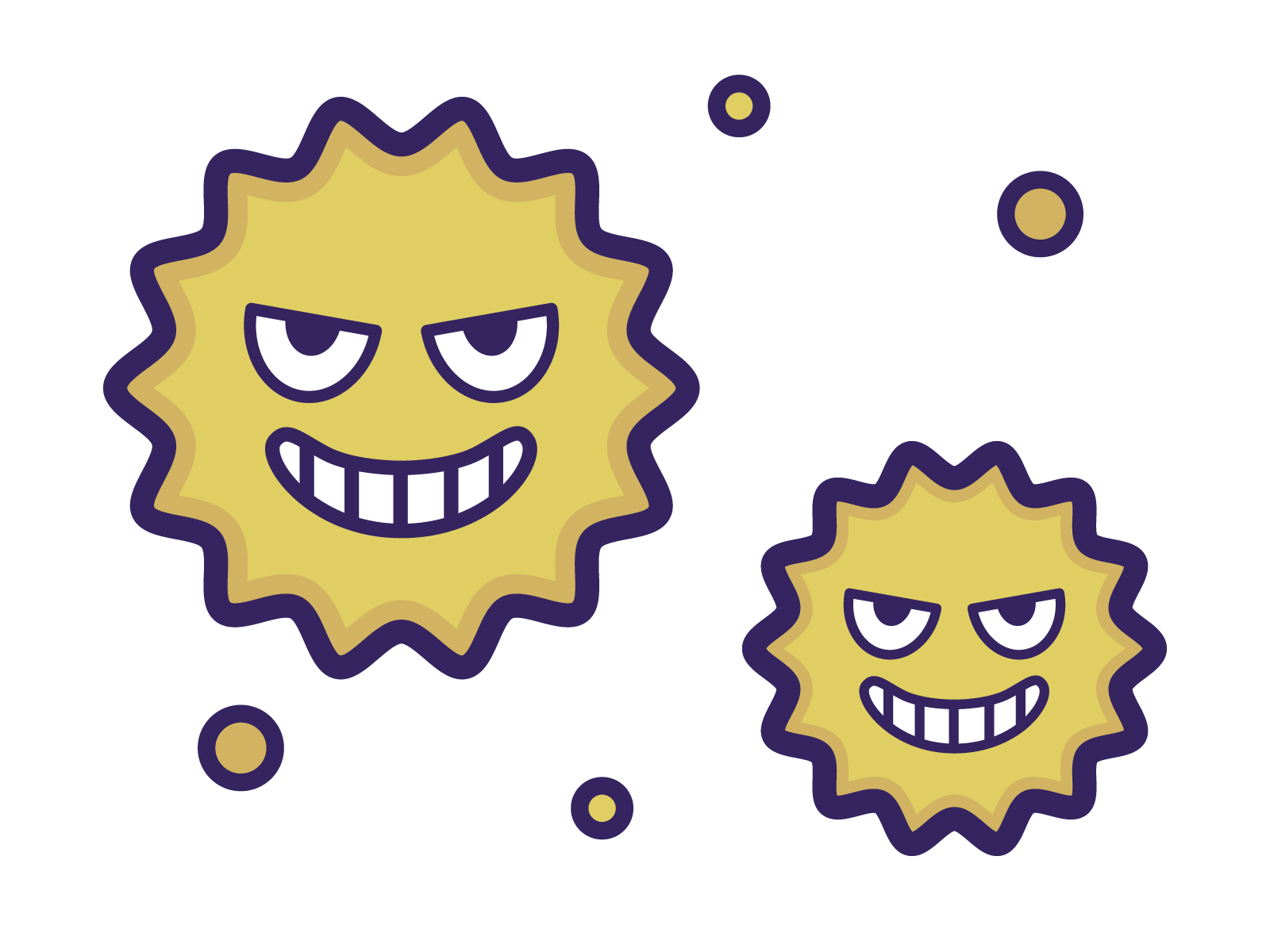
襖にカビが生えると、黒ずみやシミが目立ち、美観を損なうだけでなく健康被害にもつながる可能性があります。特に和室は畳や障子など湿気を吸収しやすい素材が多く、カビの発生リスクが高い空間です。まずは、原因を正しく知ることで、適切な対処や予防につなげましょう。
湿気と通気性の悪さが大きな要因
襖にカビが生える最も大きな原因は湿気の滞留です。特に以下のような状況では、襖紙に湿気が吸収されやすくなり、カビの栄養源になります。
- 梅雨時期や冬場の結露で部屋が湿っぽい
- 押し入れや和室を長期間閉め切っている
- エアコンや除湿機を使用せず、換気が不十分
また、通気性の悪い部屋では空気がこもり、襖の裏側にも湿気が回りやすくなります。湿気が乾燥せずに残ってしまうと、表面や内部にカビが繁殖し、消毒や拭き取りだけでは対応が難しくなることもあります。
生活習慣や家具配置もカビの温床に
カビは部屋の環境だけでなく、暮らし方や家具の置き方にも影響されます。たとえば…
- 襖の近くに観葉植物や加湿器を置いている
- 襖を開閉せず、同じ位置で長期間放置している
- タンスや本棚などをぴったり壁につけて置いている
これらはすべて湿気の逃げ場を奪い、風通しを悪くする要因です。また、ペットの体温や呼気、こまめな掃除の不足も、ホコリや汚れを通じてカビの温床となりやすいので注意が必要です。

襖の張替えは、信頼できる専門業者に相談するのが安心です。「あたらし(国家資格職人が丁寧施工)」なら、再発を防ぐ防カビ対応の張り替えをご提案いたします!見積無料!スピード対応!
電話番号:0120-6767-23
(※営業時間外は留守番電話で受付)
\受付時間/午前7:00〜(土日祝日も対応)!/
すぐできる!襖のカビ除去方法と注意点
襖にカビが生えてしまったら、できるだけ早く対処することが大切です。初期の軽いカビであれば、自分で掃除して落とせるケースもあります。ただし、使用する薬剤や掃除の方法を間違えると、襖紙を傷めたり、カビを広げてしまうリスクもあります。ここでは、安全かつ効果的にカビを除去する方法と、やってはいけないNG例を紹介します。
エタノールや漂白剤を使った掃除方法
カビの初期段階なら、消毒用エタノール(70~80%)を使った掃除が効果的です。以下は主な手順です。
| 使用薬剤 | 手順 | 注意点 |
| 消毒用エタノール | スプレーで吹きかけ→布で優しく拭き取る | 火気厳禁・換気必須 |
| 塩素系漂白剤(薄めて使用) | 綿棒や布で塗布→拭き取り→乾燥 | 色落ちの可能性あり・事前に目立たない場所でテスト |
また、掃除を行う際には以下の点にも注意しましょう。
- 襖紙の素材によっては、薬剤でシミや色抜けが起きやすいため、必ず目立たない箇所でテストしてから使用する
- 拭き取り後は、乾いた布で水分をしっかり除去し、風通しを確保することでカビの再発を防ぎやすくなる
- 使用後は必ず換気を行い、薬剤が部屋に残らないようにする
やってはいけないNGな掃除方法とは
一見効果がありそうでも、襖には不向きな掃除方法がいくつかあります。以下は避けるべきNG例です。
- 水拭きや濡れ雑巾でゴシゴシこすること
襖紙が破れたり、逆にカビの栄養源となる水分を与えてしまうおそれがあります - スチームクリーナーの使用
高温の蒸気は襖紙や下地を劣化させる原因になります - 重曹・クエン酸などの自然派洗剤の使用
一部の襖紙ではシミや変色のリスクがあるため避けた方が無難です
また、手垢やホコリがついた状態で薬剤を使うと、かえって汚れが広がることもあるため、まずは軽く乾拭きして表面を整えてから作業するのがおすすめです。
再発を防ぐ!カビ対策のコツと生活習慣の見直し
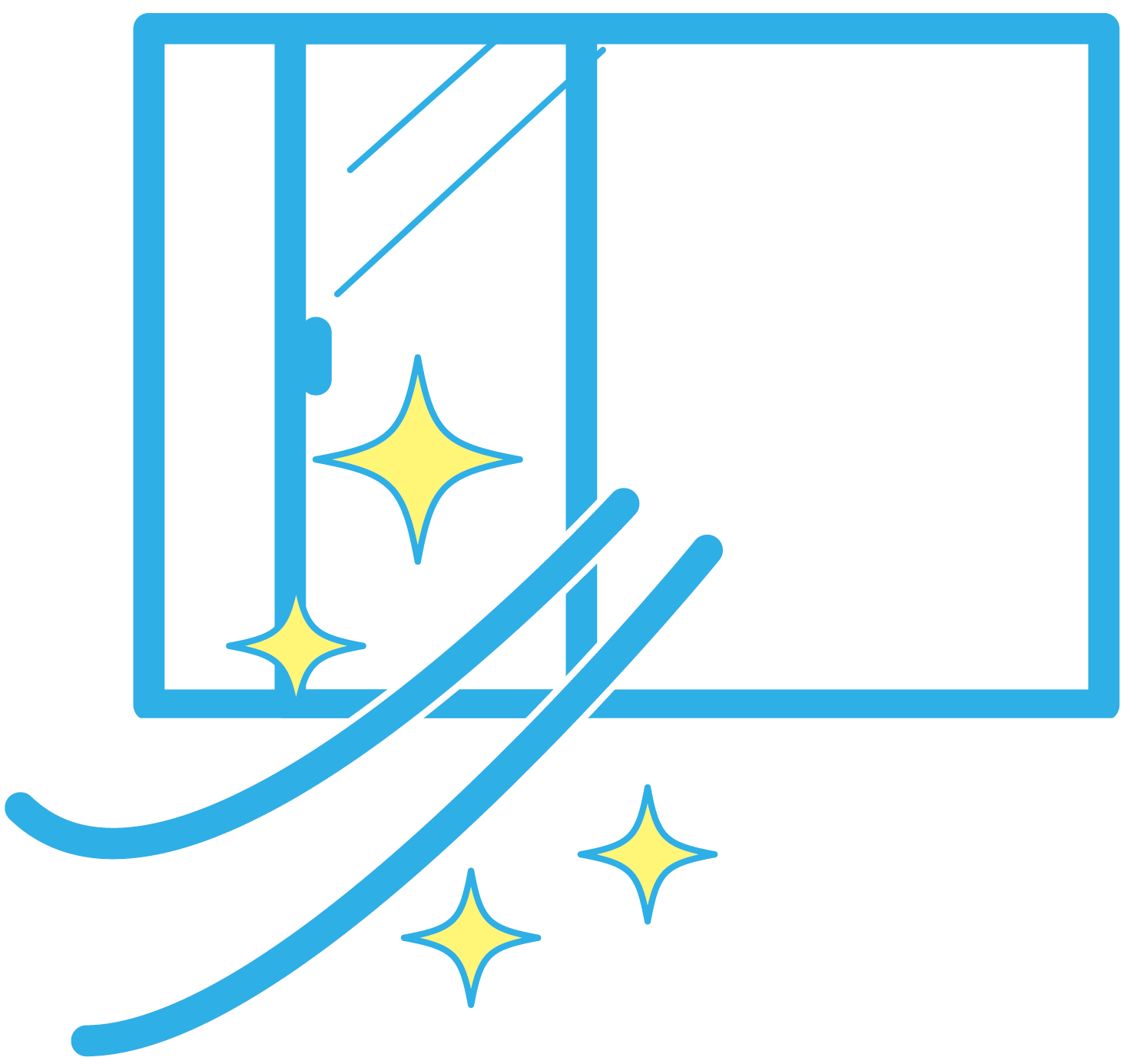
せっかく襖のカビを除去しても、また同じ場所にカビが生えてしまっては意味がありません。カビは湿気と栄養源(ホコリ・手垢など)が揃うと再発しやすいため、日常的な生活習慣の見直しが重要です。ここでは、カビの再発を防ぐために意識したい換気・除湿の基本と、収納や掃除でできる湿気対策の工夫を紹介します。
日常的な換気・除湿が最大のカギ
カビの発生を防ぐうえで、もっとも基本的かつ効果的なのが「湿気をためない環境づくり」です。
- 晴れた日には、朝と夕方に数分間窓を開けて換気を行うのが基本
- 可能であれば日中も定期的に換気して、こもった湿気を逃がす
- エアコンの除湿機能や除湿機を活用して、空気中の湿度をコントロール
- 襖がある和室は、布団の湿気や加湿器の影響を受けやすいため要注意
- 風通しの悪い部屋には、サーキュレーターなどで空気を循環させると効果的
- 湿度が高い日は、こまめな換気と除湿の併用がカギ
また、雨の日や梅雨時期には、室内に湿気がこもりやすいため、室内干しやペットの水回りの近くの襖には特に注意が必要です。
カビは「静かに広がる」ため、湿度に気を配ることが最良の予防策となります。
湿気を溜めない収納・掃除の工夫
襖がカビやすい場所のひとつが、押し入れや収納スペースです。ここにも湿気やホコリ、手垢が蓄積しやすい条件がそろっています。
- 押し入れ内の荷物は詰め込みすぎず、適度な空間をあける
- すのこや除湿シート、備長炭などの湿気吸収アイテムを活用
- 季節の変わり目には、収納の中身を一度出して拭き掃除をする
- 掃除の際はホコリを溜めないよう、こまめに乾拭きするのがポイント
特に襖紙の表面は繊細な素材でできているため、水拭きではなく、乾いた雑巾での拭き取りを基本とします。
また、襖の近くに家具を密着させないように配置することで、空気の流れができ、湿気がこもりにくくなります。
まとめ
襖にカビが発生すると見た目の悪化だけでなく、健康や住環境にも悪影響を及ぼします。まずは原因を知り、家庭でできる除去方法と日々の予防策をしっかり実践することが大切です。
カビが再発しないように、湿気対策や生活習慣の見直しを継続しましょう。もし状態がひどい、または除去が難しい場合は、無理せず専門業者に相談するのも選択肢のひとつです。清潔な和室を保つためには、「カビを落とす」「生やさない」の両面からの対策が欠かせません。

襖のカビにお困りの方へ――もし張り替えを検討するなら「あたらし」にご相談ください。
カビが深く根を張っていたり、繰り返し再発してしまう場合は、張り替えによる根本対処が効果的です。
私たち「あたらし」は、和室の快適さを守るため、カビや劣化に強い襖を高品質・低価格でご提供しています!見積無料!スピード対応!
- 国家資格職人が丁寧に施工
- ペット対応・防カビなどの紙も多数取り扱い
- 追加費用なしの明朗会計、短納期で納品可能
電話番号:0120-6767-23
(※営業時間外は留守番電話で受付)
\受付時間/午前7:00〜(土日祝日も対応)!/
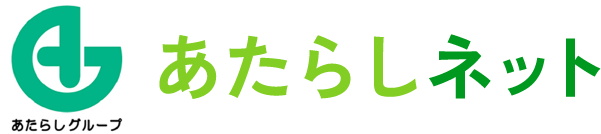
 障子相談
障子相談 電話相談
電話相談